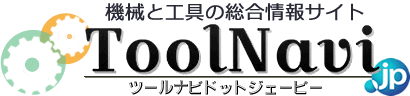自動車部品、中国で攻める
日系自動車部品メーカーが中国市場で攻勢をかけている。完成車メーカーが中国で販売を伸ばしていることを背景に、車部品メーカーは相次ぎ、現地の生産能力の増強や新製品の投入などに動いている。中国では小型車の減税措置が昨年12月末で終了し、反動減も懸念されたが、2018年も需要は底堅いとみる向きが大勢だ。巨大市場の中国で受注機会の拡大を図るため、車部品メーカーは積極的な投資に踏み切る。
■新車販売、世界一独走
【反動減は軽微】
中国自動車工業協会は、17年の新車販売総数が過去最高を更新した16年を約140万台上回る、約2940万台になるとの見通しを示している。17年1月―11月の新車販売は、前年同期比3.6%増の2584万台と堅調に推移。特に日系完成車メーカーが好調で、トヨタ自動車の同期間の累計販売は同7.5%増の約118万台、日産自動車は同12%増の約133万台、ホンダは同16.6%増の約130万台と伸長している。18年の不安材料として小型車減税の終了があるが、ある部品メーカー首脳は「今のところ需要の先食い状況にはなっていない。影響は軽微だろう」と話す。
トヨタは18年のグループ世界販売台数(ダイハツ工業、日野自動車を含む)が中国や東南アジアの伸長を見込み、17年見込み比1%増の1049万5000台と過去最高を計画している。「(世界各地の中で)販売が伸びているのは中国くらい」(トヨタ首脳)とし、中国市場の成長性に期待を寄せる。
トヨタ系部品メーカーも事業拡大の好機とみて、着々と中国での生産能力増強に動いている。アイシン精機は自動変速機(AT)を増産する。子会社でAT世界最大手のアイシン・エィ・ダブリュ(AW)を中心に生産体制を強化する。まずは約1000億円を投じ、日本や中国で工場を新増設する。20年にATの世界生産台数を18年3月期比約25%増の1250万台に高める方針で、今後は中国などの完成車メーカーと合弁工場をつくることも検討する。
ATは手動変速機(MT)からの置き換わりなどで世界的に需要が伸びているが、電気自動車(EV)には使われず、中期的に需要減少の懸念もある。アイシン精機の伊原保守社長は、「今回の投資は5年程度で回収できる」と話した。ただ、さらなる増産はリスクもあるとして、中国の自動車メーカーなどとの合弁工場の設置も検討する。
【コスト減にも】
豊田合成は20年をめどに、樹脂製の燃料導管「樹脂フューエルフィラーパイプ」の年産能力を世界で15年実績比約4.5倍の約500万本に引き上げる。中国・天津市の工場で18年から新たに生産を始めるほか、日本、米国、欧州、アジアの各拠点も増強する。樹脂製導管は重さが金属製の従来品の約半分で、コスト減にもつながるとみて受注活動を強化する。
18年3月期に中国で前期比9.3%増の148万台の販売を計画する日産。同社との取引の多い車部品メーカー各社も同国でのビジネスチャンスの拡大を狙っている。
パイオラックスは、中国の燃料蒸発ガスの排出抑制強化に対応するため、18年秋にも燃料の透過防止性能を高めた樹脂製燃料タンク向けバルブ「2K」部品の中国生産に乗り出す。2層構造のため、低浸透性が高い部品で中国の現地タンクメーカー大手から受注を獲得。パイオラックスの湖北省・武漢市にある工場での生産を軸に検討しており、月産1万台を計画する。島津幸彦社長は「今回の受注は日系完成車メーカー向けだが、これをきっかけに実績を積み上げて、中国の現地車メーカーとの取引にもつなげたい」と意気込む。
ヨロズは約13億円を投じ、広州市のサスペンション部品工場に型締め力3500トンのトランスファープレス機を導入した。17年4―9月期は、タイとインドネシアで売り上げが減少したものの、中国がカバーし、アジア地域全体の売上高は前年同期比1.8%増の約261億円。好調な中国で投資を拡大して、サスペンション部品の現地生産能力を増強する。河西工業も武漢市に天井部品の生産会社を設立し、17年7月からルーフ部品供給を開始した。生産能力は年間20万台規模で、天井部品事業を主力のドア内装事業に並ぶ事業の柱に育成する。
【独立系が強気】
ホンダ系や独立系車部品メーカーの動きも活発だ。ホンダ系のジーテクトは11月に、武漢市で車体部品を生産するWAPACで溶接組み立ての第2工場新設を決めた。同社は上海市にリサーチ拠点を設置しており、EVに必要な軽量で剛性の高い車体部品の現地開発などを武器に、中国市場での取引拡大を加速させる。独立系の小糸製作所は福州市にある「福州小糸大億車灯」に数億円を投じ、第3棟(約8000平方メートル)を増設する。稼働は18年夏の予定。中国での車生産増加に伴い増え続けるヘッドランプとリアコンビネーションランプの需要に対応する。
新車販売台数で世界一を独走する中国。17年も前年を上回ることは確実で、9年連続で世界トップの自動車大国となる見通しだ。米国では新車販売の減速感が漂う一方で、中国は18年以降も安定的に成長するとみられる。車部品メーカー各社は商機を逸しないように現地の生産能力を増強するなどして事業拡大を狙う。