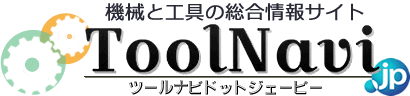工作機械、活況が一転 年間受注6000億円減少
2019年の工作機械の市況は、祭りの後の静けさに包まれた1年だった。18年は年間受注高が過去最高の2兆円に迫り、空前の活況と言われた。だが、19年は6月に好不調の判断目安である月1000億円を32カ月ぶりに割り込み、8月には76カ月ぶりに月900億円を下回った。元凶の米中対立の余波は大きく、19年の受注高は1兆2000億円台に落ち着きそう。前年からは6000億円程の落差がある。
「山から次の山へ、尾根伝いに歩いている」。日本工作機械工業会(日工会)の飯村幸生会長は1月に開いた新年行事で19年の工作機械業界をそう言い表した。ただ、実際は山から次の山へと谷を歩くような1年だった。
日工会は年初に定めた年間受注高目標の1兆6000億円を、9月に3500億円ダウンの1兆2500億円に見直した。米中摩擦、中国の設備過剰などの中、当初想定を超える厳しさがある。17―18年初めは全世界同時好況といった状況だったが、19年はその対極の様相だ。米国の受注が弱含み、日本、ドイツの停滞が目立つ。
ただ、工作機械業界の静けさは受注面に限られる。短中長期視点の技術開発、市場開拓はギアが1段上がった感もある。すごそこに迫った第5世代通信(5G)時代を見据えた社内検証が急ピッチで進む。ファナックやDMG森精機はそれぞれ自社工場での実証テストに乗り出した。人工知能(AI)の実装も本格化し、ヤマザキマザックは加工条件を補正するAI搭載の5軸加工機を発売した。
社会課題の労働力不足を背景に自動機器との融合も盛ん。オークマは産業用ロボットのパッケージ対応機種数を3倍以上に拡大した。一方、成長性を秘めたインドではツガミやDMG森精機が生産拠点の整備に動いた。
工作機械の景況は数年周期で山と谷を繰り返す特性がある。好転は20年夏前とされる。跳躍のために膝を抱え込んだ1年と言えるだろう。