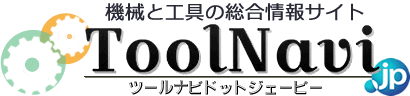1月の機械受注、8.2%増 課題は消費喚起
内閣府が14日発表した1月の機械受注統計(季節調整値)によると、設備投資の先行指標である「船舶・電力を除く民需」は前月比8・2%増の8723億円と、2カ月ぶりに増加した。同日が集中回答日だった2018年春闘も好調な企業業績を反映し、前年実績を上回る賃上げが相次いだ。
ただ3%以上の賃上げ企業は限定的で、景気拡大の恩恵が企業分門から家計部門に波及するかは依然不透明な状況にある。
1月の機械受注の基調判断は「持ち直しの動きがみられる」に据え置いており、堅調な投資が継続している。
1月の内需のうち、製造業は前月比9・9%増の4094億円、非製造業は同4・4%増の4654億円と、いずれも2カ月ぶりに増加した。
製造業は造船業が同78・0%増、化学工業が同37・9%増、スマートフォン関連などが堅調な情報通信機械が同29・5%増など、17業種のうち10業種が増えた。非製造業は不動産業の同約2・8倍など12業種中6業種が増加した。
官公需は同18・7%減の2076億円、外需は同11・6%増の1兆971億円、中小企業から受注する代理店は同3・1%減の1156億円。これらと内需を合わせた受注総額は同4・5%増の2兆4745億円で、2カ月ぶりの増加だった。
日本経済は、世界経済の拡大に伴う輸出増や堅調な設備投資など企業部門がけん引し、今後も緩やかな景気回復が期待されている。問題は停滞する個人消費などの家計部門の行方。安倍晋三政権は5年目の“官製春闘”である18年春闘で3%以上の賃上げ率を実現し、消費喚起につなげたい意向を示す。
だが14日の集中回答日は前年実績こそ上回る企業が相次いだものの、「3%以上」は高い壁だった。さらに森友学園問題をめぐる国会紛糾により、働き方改革関連法案の行方には不透明感が強まる。今後国会が混乱し、安倍政権の安定性に疑問符が付けば、消費者マインドにも少なからず影響を及ぼす可能性がある。